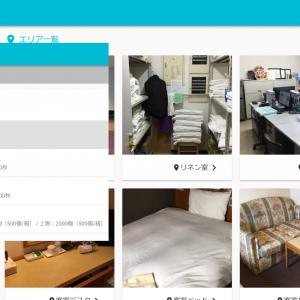前回、「作る」事に集中しすぎて、作り手が妄想領域(こんな機能もあったらいいだろな~)に突入してしまい、不要なプロダクトを時間をかけて作ってしまう悲しい惨劇について書きました。
そして、その悲しい惨劇を避ける方法「顧客が本当に望んでいることを見つけ出し、その望みに製品やサービスを合わせていくという地道な作業を怠らない」についても紹介しました。
では、メンバーが実際にどのようなプロセスを進んでいけば良いのでしょうか。
1.全体のグランドビジョンを明確にする
-誰の
-どんな課題を
-どのように解決するのか2.最初に使ってくれるお客さん(アーリーアダプター)がそのサービスやプロダクトに対して、本当に価値があると思ってくれる「提供価値」の仮説を立てる(セルスタート)
3.新しいお客さんがそのサービスやプロダクトに対して、どのような価値があると思うかの仮説を立てる(アクセル)
4.実用最小限のプロダクトを作る
5.最初に使ってくれるお客さん(アーリーアダプター)に使ってもらい、計測する
-定性的な計測: 何が気に入って、何が気に入らなかったかをデータとして記録
ー定量的な計測: 何人が利用して、何人が役に立ったかをデータとして記録6.計測データから、改善点を見つけるもしくは2と3の仮説を方向転換すべきかを考える
7.考えた内容(アイデア)を反映した新しいプロダクトを作る
8.5~7を繰り返す中で、 最初に使ってくれるお客さん(アーリーアダプター) がインフルエンサーとして勝手に薦めてくれるようになる
この中でも重要になってくるのが、「5」です。
市場が安定的に推移し、リソース(お金も人)も潤沢で、マクロ的な市場分析を行っている余裕がある場合は、「5」をしなくても、「1」~「3」において、綿密な市場調査と事業計画を行い、ホワイトボードで緻密な戦略を作った後、エンジニアを投入して壮大なプロダクトを作り、テレビCMなど多額のPRや広告を打てば、計画通りに進んでいきます。
ただ、これまでの時代と異なり、市場が常に変動する不安定な時代となり、壮大なプロダクトを作っても直ぐに時代遅れになってしまう可能性が高くなってしまいました。
そこで、「5」を行う重要性が高まってきたのです。エンジニアなどのプロダクトの作り手が実際にそのプロダクトを使用するお客さんの所に行き、どんな環境でどんな使い方をして、どの部分に価値を置き、どの部分に不満を持つかを直に聞くことが重要なのです。
まさに「現場」に行くことの重要性です。どうしても作り手の性格上、作る(集中)モードに入ってしまうと、机の前に張り付きになり、お客さんから最も遠い所にいってしまう傾向にあります。ですので、「作る」モードと「計測」モードを短期にぐるぐると回転できるように、意図的にプロジェクトの中でその隙間を作ることが非常に大事になります。