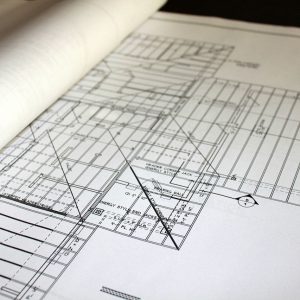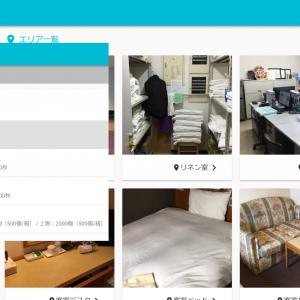日々、ホテル業務や清掃業務に携わっていると、リアルな現象が毎度起きます。
それは人と人のコミュニケーションによる問題(もめごと)であったり、お客様が転んでぶつかって壁に穴が空いたり、急にシャワーのお湯が出なくなったり、壁に変な染みが出てきたり。
リアルな現象に対して、毎回瞬時に対応していると、だんだんその解決方法の精度や対応力が上がってきます。その中で、徐々に原因と解決を繋ぐツリー構造の全体像が見えてきて、また日々のリアルな現象と解決を繰り返す度にそのツリー構造が縦にも横にも増築されていきます。
アナログ知らずに汎用語で全体像を作る軽薄
このツリー構造を先に作ってから、そこから派生する細かな打ち手を考えていたのが、過去に働いていたコンサルティング時代の手法でした。
「縦軸」、「横軸」だと言って、それっぽい汎用単語をMECEに並べて、アナログをまとめる為の土俵を作ってから、出し尽くしのツリー構造を派生させていきます。
ただ、そうすると起こる現象が必要のない領域まではみ出して出し尽くしを行う為、どんどん内容の薄い、どの領域・業界でも当てはまるような全体像と打ち手がわんさか出てきてしまいます。
実際には現場では使えないものとなり、最終的には教科書として企業の隅っこにしまわれてしまいます。
アナログからしか生まれない意味ある単語で形成すること
全体像は非常に重要なものですが、最初に作るべきは全体の骨格ではなく、リアルなアナログ現象のボトムアップです。
ボトムアップしやすい箱だけ用意しておき、そこに現象が起きる度にちゃんと入れていきます。すると、ボトムアップの知見が履歴として見える化されて、徐々に構造化できるようになります。
そうなれば、ある程度の関数をもったリアルで固められた(軽薄な言葉のない)ツリー構造が作る事ができます。このツリー構造も基本的に終わりはなく、リアルなボトムアップを繰り返すたびに再現なく枝葉や幹が増幅していくものです。
本当のAIは過去からの学習ではなく、現在の認知と関数の更新
このリアルが積み上がった事による究極のトップダウンこそがAIとなります。
ただ、究極のトップダウンに終わりはなく、現状のAIをもてはやすとすれば、それは過去のデータによって作られた途中経過のツリー構造をただもてはやしているだけだという事です。
その辺りをしっかり気を付けながら、少し全体像が見えただけで分かった気にならない、それはアナログの切れ端をまだ集めている途中だと言い聞かせていきたいと思います。